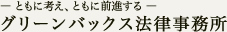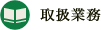身内が罪を犯し、或いは犯したものと疑われて逮捕されてしまったという場合、逮捕された者(被疑者)の配偶者や親、子、兄弟姉妹などは、被疑者のために弁護人を選任することができます。
多くの場合、一度捜査機関に逮捕されると、その後は勾留という手続によって身柄拘束が継続され、被疑者は長期間、外部と隔離されてしまうことになります。
刑事手続について十分な知識や情報もなく、外部から長期間隔離された状況において、捜査機関からの取り調べ等を受ける者の精神的な負担は非常に大きいものであり、被疑者が少年の場合には特に深刻です。
被疑者に対して、刑事手続に関する必要な情報を提供したり、外部との連絡の機会を設けることで、このような精神的負担を少しでも軽減するためにも、早期に弁護人(付添人)を選任することは極めて重要といえます。また、裁判や審判といった最終的な処遇を決める手続において、有利な事実などを十分に斟酌してもらい、妥当な判断を求めるためにも弁護人(付添人)の存在は不可欠です。
以下では、成人の刑事事件と少年事件に分けて、手続の流れなどを説明するとともに、各段階における弁護人(付添人)の役割の概要を紹介します。
成人の刑事事件
典型的な刑事手続の流れ

1.捜査手続
1-1. 手続の流れ (身柄事件の典型)
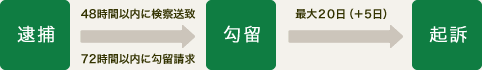
1-1-1. 逮捕
事件が発生すると、捜査機関がこれを察知して捜査を開始します。
捜査の結果、多くの場合、特定の人に疑いがかけられ、警察によって逮捕されます
逮捕されると、警察に連行されたうえ、留置施設で身柄を拘束され、警察官による取り調べを受けます
警察官は、逮捕してから48時間以内に検察官に身柄や証拠書類を送らなければなりません
1-1-2. 勾留
証拠書類とともに身柄の送致を受けた検察官は、留置した状態での捜査が必要と考える場合には、裁判官に勾留請求します。(送致から24時間以内かつ身柄拘束から72時間以内に勾留請求)
勾留の決定が出ると、原則10日間、身柄拘束が継続します。
( 勾留3要件:「家なしor逃げそうor隠しそう」 )
さらにやむを得ない事情がある場合には最大10日延長されます。
(ただし、実際は延長されるケースの方が多い)
勾留期間の満期までに検察官は起訴、不起訴を決定します。(起訴権限は検察官のみが持つ)
起訴後も公判の終了までは勾留(被告人勾留)が継続されます。
※ 勾留されない場合
勾留の要件がない場合は釈放となり、在宅の状態で捜査が行われます
この場合、勾留される場合と異なって身柄拘束についての時間制限がないため、起訴、不起訴の決定は20日以内に行われるわけではありません
1-2. 捜査段階における弁護人の役割
1-2-1. 早期の接見
疑いをかけられて逮捕された人(被疑者)は、一般的に逮捕直後が最も不安や動揺が大きいとされています。
そこで、何よりもまず、早期に被疑者が留置されている場所(警察署)に接見に行くことが重要です。とくに、接見禁止といって、弁護人以外の者と接見することが禁止されている事件の場合は、外部環境から隔離された被疑者の不安は大きいといえます。
弁護士の場合、一般面会が認められていない時間帯でも接見をすることができる場合があります。
1-2-2. 状況の説明
弁護人が被疑者と接見した際には、被疑者が置かれている立場や今後の手続の流れを被疑者に説明します。
多くの被疑者は、逮捕後、自分がどのような扱いを受けるのか、どのように手続が進んでいくのかについて十分な知識や情報を有していません。
そこで、弁護人は、これらの点を被疑者にわかりやすく説明します。
1-2-3. 権利の説明
被疑者は、逮捕直後の不安・動揺、長期間の身柄拘束による疲弊等が原因して、実際の事実と異なる不利な内容の自白をしてしまうことが少なくないとされています。
そこで、弁護人は、被疑者には黙秘権、署名拒絶権等の権利があり、捜査機関に対して話したくないことを無理やり話す必要はないこと、事実と異なる内容、被疑者自身が話した内容と異なる内容を記した調書が作成された時は、調書への署名等を拒絶できることなどを被疑者に説明します。
1-2-4. 関係者との連絡
特に弁護人以外の者との接見が禁止されている場合は、家族であっても被疑者と会うことができないことから、弁護人が被疑者の家族や友人、その他の関係者との連絡役を担います。
1-2-5. 早期の身柄解放に向けた活動
明らかに嫌疑が不十分である場合や、罪を犯したことが事実であっても、犯罪の軽重その他の諸般の事情に照らし、長期の身柄拘束の継続を伴ってまで裁判を行うことが相当でない場合等には、検察官に対し、不起訴や略式による起訴といった処分をもとめる意見を述べ、早期の身柄解放を求めます。
その他、犯罪の被害者がいる場合には、被害者との示談の有無は被疑者の処遇を判断するにあたって重要であることから、早期に示談の成立を目指します。
2.起訴手続
2-1. 起訴の種類
| 正式起訴 | 公開の法廷での正式な裁判を求めるもの |
|---|---|
| 略式起訴 | 軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料相当)について、公判廷を開かずに書面審理のみに基づく刑の言渡し(略式手続)を求めるもの ※公判開廷日まで待つ必要がなく、早期の身柄開放が望めるという点ではメリットが大きい |
2-2. 起訴以外の処分
捜査機関による捜査の結果、被疑者が罪を犯したと認めるに足りる十分な証拠が収集できなかった場合には、嫌疑なし或いは嫌疑不十分によって不起訴となります。
また、罪を犯したことが明らかであっても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況に照らして起訴が相当でないと判断される場合には、起訴猶予相当として不起訴となります。
2-3. 起訴後公判までの期間における弁護人の役割
2-3-1. 公判に向けた準備
公判期日の手続(後述)について被告人に流れを説明し、そこでどのような主張(弁論)をするか被告人とともに方針を検討・協議します。
2-3-2. 裁判で提出する証拠の収集(起訴後に限らない)
裁判で提出すべき、被告人・弁護人の主張を裏付ける証拠を収集・整理します。
無罪を主張する場合には、当然、無罪の裏付けるあらゆる証拠を収集する必要があります。
また、被告人自身が罪を認めている自白事件の場合も、被害者がいる場合には示談を取りつけたり、適切な情状証人を探したりして有利な情状事実を主張し、より軽度の量刑を求めるための証拠を収集します。
2-3-3. 保釈の請求
捜査段階で勾留によって身柄が拘束されている場合、通常、起訴後も身柄拘束が続きますが、起訴後については、保証金を納めることを条件として身柄の解放を求める保釈制度があります。
そこで、起訴後も身柄拘束が続いている場合で、保釈を求める理由がある場合には、弁護人としては、被告人やその家族等の意向により、保釈の請求を行います。
ただし、いかなる場合にも保釈が認められるわけではありません。
3.公判手続
3-1. 公判手続の流れ

3-2. 公判手続における弁護人の役割
2-3-1. 検察官が提出しようとする証拠への対応
検察官は、被告人の有罪、厳罰を基礎づける資料として、公判期日において、さまざまな証拠を裁判所に提出しようとします。
とくに被告人が無罪を主張している事件においては、弁護人はこれらの検察官が提出しようとする証拠について、法律に基づいてその提出を阻止したり、或いは検察官が請求した証人の証言を弾劾したりします。
また、被告人が罪を認めている事件であっても、検察官が起訴されている罪とは別の余罪に関する証拠を提出しようとする場合には、余罪を考慮して不当な量刑判断がなされることがないよう、弁護人は法律に基づいてその提出を阻止します。
2-3-2. 弁論を基礎づける証拠の提出
とくに被告人が無罪を主張している事件においては、弁護人は公判前 までに準備した無罪を基礎づける様々な証拠を裁判所に提出します。また、被告人の無罪を基礎づける事実を証言してくれる証人が存在する場合には、その者の法廷での証言を証拠とするよう裁判所に求めます。
被告人が罪を認めている事件であっても、執行猶予を求めたり、より軽度の量刑を求めるべく、被告人にとって有利な情状事実を基礎づける証拠(示談書、謝罪文、反省文等々)を裁判所に提出します。また、被告人の監督を誓約する者の存在も、通常、量刑を判断するにあたって被告人に有利な情状として考慮されるため、そのような情状証人が存在する場合には、その者の法廷での証言を証拠とするよう裁判所に求めます。
2-3-3. 最終弁論
検察官・弁護人からの証拠の提出、証人の尋問等々、証拠調べの手続が全て終了すると、検察官からの論告(検察官の求刑意見)に続いて、弁護人が最終的な弁論(有罪・無罪、量刑の如何についての弁護人意見)を述べます。
弁護人は、この最終弁論において、それまでに提出したすべての証拠を総合して、被告人の無罪を説得的に主張したり、或いは、被告人が罪を認めている場合であっても、執行猶予を付した判決が相当であることなどを説得的に主張します。
少年事件(被疑者等が20歳未満の刑事事件)
1.少年事件の流れ(成人の刑事事件との相違)
1-1. 逮捕・勾留(勾留に代わる観護措置)
捜査段階における逮捕、勾留については、成人の刑事事件と概ね同様です。ただし、少年の場合には、逮捕後の勾留に代えて観護措置に付することもできるとされており、その場合は、通常の勾留のように警察の留置場で身柄を拘束されるのではなく、少年鑑別所に身柄が置かれることとなります。
1-2. 起訴ではなく家裁送致
成人の刑事事件の場合、嫌疑についての捜査が終了すると、検察官は、起訴・不起訴の判断をすることになりますが、少年事件の場合、検察官は、全ての事件を家庭裁判所に送致することとされています。
ただし、一定の重大な事件については、いったん検察官から事件の送致を受けた家庭裁判所が再度これを検察官に送致し(逆送)、逆送を受けた検察官が起訴をすることとなります。
1-3. 少年鑑別所における観護措置
通常の少年事件で、事件が検察官から家庭裁判所に送致された後には、それまで勾留によって警察署の留置場に置かれていた少年の身柄は、観護措置という手続によって少年鑑別所に移され、審判までここで過ごすことになります(観護措置決定がなされなかった場合には、身柄は解放され、自宅に戻ることができます)。
少年鑑別所は、制裁を与えることを目的とする施設ではなく、少年に対する処遇を判断する参考とすべく、行動観察・心理テスト・鑑別所技官との面接などを通じて、少年の性格、資質、生活環境などを調査する施設です。
観護措置の期間は、4週間程度となるケースが多いですが、法律上最長8週間まで観護措置を継続することが可能とされています。
1-4. 刑事裁判ではなく少年審判
通常の少年事件(逆送によって起訴となる一部の重大事件を除く少年事件)では、少年に対する最終的な処遇を決める場は、刑事裁判ではなく少年審判です(ただし、そもそも審判を行わない「審判不開始」の決定がなされる場合もあります)。
少年審判は、刑事裁判と異なり非公開で行われます。
1-5. 少年審判における処分の種類
通常の少年事件における少年に対する処分の種類は、主として、不処分、保護観察、少年院送致の3つです(これら以外に児童自立支援施設等への送致もあり得ます)。
2.弁護人(付添人)の役割
検察官により事件が家庭裁判所に送致されると、捜査段階における弁護人の任務はいったん終了し、弁護人は、改めて、「付添人」という立場で活動することになります(厳密には、改めて弁護人を付添人として選任することが必要です)。
少年事件における弁護人・付添人には、成年の刑事事件における弁護人と同様、身柄を拘束されている少年との接見を通じて少年に必要な情報を提供したり、精神的負担を緩和する、少年にとって有利な事情を十分に考慮し、処分ができるだけ軽度のものとなるように弁護活動を行うという役割もありますが、このほかに、少年が人格的に成長し、非行の温床となった原因を克服していく過程をパートナーとして援助するという重要な役割があるといえます。
そのため、家庭訪問や学校訪問、職場訪問等によって少年を取り巻く環境を実際に把握し、少年の家族や関係者と協力して、少年が社会復帰した後の更生環境を整える努力をすることも少年事件における弁護人・付添人の重要な役割の一つといえます。